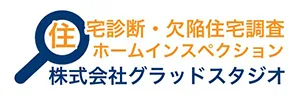中古住宅で住宅診断は義務化?費用や依頼の流れをわかりやすく解説

中古住宅を購入する際、住宅診断の重要性が高まっています。住宅診断は、安全性や資産価値を確認できる重要な手続きです。一方で「診断をするのは義務なのか」が気になる方も多いでしょう。住宅診断の実施は任意ですが、後悔のない住まい選びには必要です。この記事では、住宅診断の義務化の詳しい内容や、依頼の流れ・費用について解説します。
この記事を読むための時間:3分
中古住宅における住宅診断の義務化になるか?
不動産業者は、住宅診断の存在を告知し、希望があれば業者を斡旋する必要があります。なお、義務化されたのはあくまで説明であり、「住宅診断の実施」自体は買主や売主の任意です。
住宅診断の義務化はまだ先でしょう。
残念ながら、住宅診断はやらないで売りたいと思っている不動産業者は多く、住宅診断を入れることを伝えると
「インスペクションをすると他に欲しがっている人に渡ってしまう」とか
「検査済証があるからインスペクションをしても意味がない」など
とホームインスペクションを渋るケースがまだあります。
私の経験からすると、ホームインスペクションを実施してその家を購入しなかったケースというのはほとんどありません。
正直申しあげますと、ホームインスペクションを渋る不動産業者は、ホームインスペクションを実施した経験が少ないと言わざるを得ません。
ホームインスペクションは、買主有利のものでなく、売主にとっても良いものなのですが、経験の少ない不動産業者は悪いところが見つかったら買ってくれないと思い込んでるだけだと思っています。
むしろ、ホームインスペクションの経験の多い不動産業者は快く協力してくれる傾向にあると感じます。
住宅診断(ホームインスペクション)とは
住宅診断とは、専門の建築士などが中立的な立場で、建物の劣化状況や欠陥を調査することです。
中古住宅の購入時に、建物の状況把握や修繕の必要性を事前に把握する手段として利用されます。住宅診断の実施により、見逃しやすい不具合を発見できるため、購入後のトラブルを防げます。
住宅診断の流れ
住宅診断は、一般的に以下の流れで行われます。
- 見積もりを依頼する
- 日程を調整する
- 住宅の調査を実施する
- 調査結果の報告書を受け取る
それぞれ詳しく解説します。
見積もりを依頼する
住宅診断を実施する場合、まずは専門業者に見積もりを依頼します。
費用は診断の内容や建物の大きさによって異なるため、事前に複数の業者から見積もりを取ることが大切です。
住宅診断という仕事は、お掃除屋さんや片付け屋さんのように目標が達成されて満足するような仕事ではありません。
報告書が提出さればいいという単純な話しではありません。もちろん報告書の内容も大切ですが、調査した建築士がどのようなことを語ってくれるか、今後、その家を購入するにあたって何に注意して、どんなメンテナンスを考えたらいいかアドバイスをもらうことも大切です。
これは、単純に金額の比較ができる問題ではありません。金額だけでなく、そのインスペクターがどういう考えのもとで調査しているか確認することも大切です。
従業員がいるインスペクション会社や調査員を派遣する会社は、動画など見栄えよく作成している場合もありますが、その動画の人が検査することは少ないです。実際に検査する人がどんな人なのかしっかり見ましょう。
不動産会社と日程を調整する
見積もりの内容に納得できたら、業者と住宅診断の日程を打ち合わせます。
住宅診断は、売主や不動産会社が立ち会う場合もあるため、関係者全員の予定を確認してスケジュールを調整しましょう。
不動産会社は、時に「インスペクションをすると他に欲しがっている人に渡ってしまう」とか「検査済証があるからインスペクションをしても意味がない」などと言ってくるでしょう。
インスペクションを実施せず購入するならば、あとで瑕疵保証の交渉はできないぐらいの気持ちで購入する覚悟であればいいと思います。
住宅の調査を実施する
住宅診断の日が決まったら、現地で調査を行います。事前に水道と電気が使用できるか確認しましょう。
診断では、建物の基礎や外壁、室内の劣化状況などを確認します。さらに、屋根裏や床下といった普段目にしにくい部分も、診断対象に含めることが可能です。どの範囲まで調査してもらえるかは、事前に業者と相談しておきましょう。
調査結果の報告書を受け取る
住宅診断が終了すると、業者から調査結果の報告書が提出されます。
何日後に報告書が送られてくるか確認しましょう。
報告書には、建物の状態や指摘事項が詳しく記載されており、物件購入の判断材料となります。報告内容をもとに、売主と修繕交渉を行うことも可能です。
中古住宅の検査項目(既存住宅状況調査)は、構造に関することと雨水の進入に関することだけです。
中古住宅の場合は、構造や雨水に関係しないこともしっかり見てくれているのかも重要なことです。
中には、必要最低限(構造と雨水に関すること)の報告をすればよいと考えている住宅診断士もします。
他よりも安いと思ったらそういうことか!とならないようご注意ください。
住宅診断の費用と負担者
住宅診断の費用や費用の負担者についても、事前に把握しておくと安心です。
費用の相場
住宅診断の費用は、建物の規模や診断内容によって異なりますが、一般的に床下と小屋裏を含んで70,000円以上が相場です。
もちろん、もっと安くやっている業者もいるでしょう。
戸建住宅の場合、延床面積が大きいほど費用は高くなる傾向にあります。事前にサービス内容を確認し、必要に応じたプランを選びましょう。
費用の負担者
住宅診断の費用は、買主による負担が一般的です。買主自身が、安心して購入できるかを判断するために、住宅診断を依頼するケースが多く見られます。ただし、売主側が負担してくれる場合もあるため、契約前に費用負担について必ず確認しておきましょう。
住宅診断は信頼できる業者に依頼しよう
一概に金額だけで判断できませんが、安いには安い理由があるとも言われます。
片付け屋さんや掃除屋さんは目的が達成さされば同じだから、安ければいいという考えもあるかもしれません。
ただ、本当に世の中を知っている人は、見積もりを取って一番安い業者はやめておけという人もいます。
要は、ホームインスペクションは金額では計り知れない部分があるので、金額だけで判断しないことが大切です。
次の記事へ
微動探査で耐震性を確認!中古住宅を安心して買う方法を紹介 »